カウント・ベイシーを語る ホブズボームのジャズ評を通して①
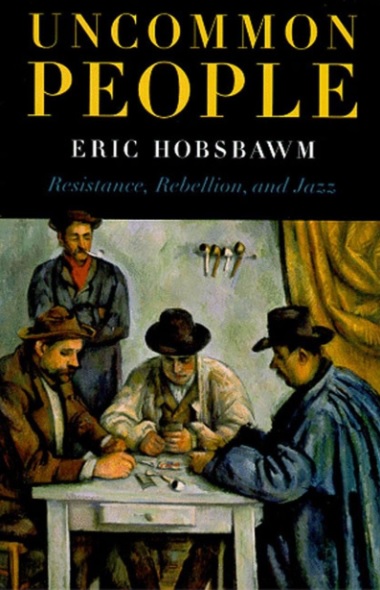
Resistance, Rebellion and Jazz
エリック・ホブズボーム(Eric Hobsbawm)は最近その伝記が日本でも出版された英国の歴史学者だが、ジャズの評論家でもあり、フランシス・ニュートンという筆名で書いたJazz Sceneには日本語訳もある。本業の歴史に関するものを中心に著作は多いが、そのうちの一冊、Uncommon Peopleは副題のResistance, Rebellion and Jazzが示すように、主に権力に反抗する人々について語るもので、反体制の姿勢を貫いたホブズボームが好んだテーマだ。ジャズは「貧しい人々にルーツを持ち発展した数少ないメジャーな芸術」であり、「フツーじゃない人々」として、シドニー・ベシェ、カウント・ベイシー、デューク・エリントン、ビリー・ホリディがそれぞれ3~10ページほどを費やして取り上げられている。ホブズボームは歴史家だから、それぞれの人物がジャズマンとして名を成したその歴史的背景についてなかなか深い洞察があり、また、ジャズについても知識と見識があるので、読み応えがある。
今回は、その中からカウント・ベイシーについて書かれたものを取り上げてみようと思う。
これはGood Morning Bluesというベイシーの自伝とThe World of Count Basieという伝記の二冊の本の書評で、1986年に発表されたものだ。ホブズボームがベイシーを含めて他者の言葉を引用している箇所についてはそのまま訳出してみよう。
1950年代にアメリカのポピュラー音楽は父親殺しを行ったとややショッキングな文章から始まる。引用されているカウント・ベイシーの言葉によればこのころは、
14番街の劇場のあたりは凄いことになっていて、夜11時ころに出向いたものだが、人が大勢で近くに行くこともできなかったのを思い出すよ。また、それからどうなったかも覚えているよ。最初のショーが始まると若者が押し合いへし合いで、手を叩いたり口笛を吹いたりして大騒ぎなんだが、いざ、我々の番になると、ポップコーンやアイスクリームなどを買いにほとんどが外に出て行ってしまい、客席がほぼ空っぽの状態で出番を務めることになる。それで、我々の番が終わると、外に行っていた連中がみな戻ってくるのさ。嘘じゃないよ。それで、地下に行って、また出番が来るまでポーカーをするわけだ。若者はジャズに関心がないのだ。中には、残って近くまで来たりして耳を傾ける人もいるので、速く演奏したり遅くしたりしてみるのだが、何も起きない。彼らは我々の演奏を聴きに来ているわけではなく、彼らにとって我々がやっていることは幕間の芸のようなものだ。仕方がないのさ。その通りなのだから、それを受け入れるしかない。
1950年代にロック&ロールがその親であるジャズを殺したというわけだ。
ホブズボームは「Good Morning Bluesを映画化するなら、年老いたバンドリーダーが無念にも負けをストイックに認めるこのイメージは映画を締めくくるシーンとして相応しいものになるだろう。」などと言っている。バンドリーダーであるカウント・ベイシーのキャリアは1980年代まで続くことになるのだが、ホブズボームが言うには、ベイシーのバンドは最も偉大なジャズバンドではなく、デューク・エリントンがその上を行くのだが、ベイシー自身もエリントンは偉大だと常に言い続けていたそうだ。
ベイシーが脚光を浴びた時代はジャズにとって黄金時代で、丁度ニューディール政策の時代(1933~1937年)と重なる。「黒人貧困層や酔っ払いの白人の音楽」であったジャズがまともに取り上げられるべき一つの芸術として、そして偉大な芸術家を生み出す土壌となったのは、政治的急進主義者によるところ大で、「彼らは情熱的にそして無私の精神で黒人とその音楽のために身を捧げ」た。ルーズベルト時代のアメリカの左翼運動がジャズの勃興のためにどれほどの貢献をしたかは未だ十分に評価されていないとホブズボームは語っている。つまり、ジャズが50年代以降停滞したのは、その背景にアメリカの左翼運動とその支持者たちが力を失ったことがあるわけだ。アメリカでは、特にポピュラー音楽は政治的状況と切り離せないのだ。しかし、ジャズに関しては当時から今までも基本的にマイノリティーに担われている芸術で、幅広い層に支持されていたわけではない。ホブズボームによれば、1973年時でジャズレコード・テープが全音楽レコード・テープの販売金額に占めるシェアはわずかに1%強で、クラシックの6%をかなり下回っている。アメリカビルボード誌の推計による2020年のジャズCDの販売シェアは2%(クラシックも2%まで落ち込んだ)、一方、ロックは41%、R&Bが15%だから、差は歴然としている。ホブズボームは別稿でジャズの低迷の原因を究明しているが、これについては別なところで触れたい。
ベイシーのバンドは当初から「譜面が読める」バンドではなく、全盛期もいわゆるヘッドアレンジメント(いちいち譜面に書かずに、大まかなメモみたいなものを全員に配り、リーダーの指示や、皆で話し合いながら、曲を作り上げていく)がほとんどで、「当時演奏する時は楽譜が4枚か5枚を超えることはなかったね。」とベイシーは回想している。当時のジャズの規準から見てさえ、尊敬に値するバンドとは言えず、ベイシーの伝記の著者、スタンリー・ダンスがバンドのメンバーに行ったインタビューによれば、
(バンドのメンバーは)一直線にポン引きと売春婦のもとに向かい、そこでぶらぶら過ごすのさ。アンディ・カークは彼らに嫌われていた。お高く留まっているというわけだ。しかし、ベイシーは彼らと共にどん底生活を味わい、彼らと一緒に酔っぱらった。彼のズボンなどつぎはぎだらけだったが、ベイシーのバンドはすべてそんな感じだった。
アンディ・カーク(Andy Kirk)は同じカンザスシティで活躍していたバンドCloud of Joyのリーダーで、ベイシーのライバルとも言える存在だった。後年、チャーリー・パーカーも短期間だが在籍しており、トランペットセクションにはファッツ・ナヴァロもいて、メンバーは充実していた。リーダーのアンディ・カークは音楽教育を受けていたので、もちろん譜面も読め、アレンジャーには女性ピアニスト、メリー・ルー・ウイリアムスがおり、当時としては進歩的なバンドだった。ベイシーバンドとは対照的だった。しかし、「合衆国にまたがってミクロネシア諸島のように散在する下宿屋、バー、クラブのような自給自足的な小さな島々を渡り歩く黒人プロミュージシャンのコミュニティの存在」がジャズと言う音楽にとっていかに重要だったかを如実に示す」もので、ジャズの発展にとってはベイシーバンドのような存在が欠かせないものだったのだ。
ベイシーバンドの名トランペット奏者、ハリー・“スウィーツ”・エディソン(Harry “Sweets” Edison)によれば、
俺たちはおんぼろバスから出てくるたかがカウント・ベイシーのバンドさ。だが、いったんバンドスタンドに上がったら猛烈にスイングする。ランスフォードの奴らを散々痛めつけてダンスホールから追い出してやったこともあった。
ランスフォードとはジミー・ランスフォード(Jimmy Lunceford)のことで、彼も大卒のミュージシャンであり、自らバンドを率い、編曲に才能を見せた。アンディ・カークと同じで、お高く留まっているバンドを上回るすごい演奏をしてみせたというわけだ。
バンドリーダーとしてのベイシーの強みはこうした黒人のプレイヤーが感じるままのジャズのエッセンスを引き出す能力にあるとホブズボームは述べている。
結果的にベイシーのバンドは創造的なソロプレイと気分を高揚させる集団プレイの驚くべき結合を生み出し、バンドは類まれな個人的才能を持つ集団を引き寄せ、それをキープした。
ミュージシャンとしてベイシー自身は並みのピアノプレイヤーで、彼と彼のバンドを見出したジョン・ハモンド(John Hammond)に感謝してこう述べている。
ジョン・ハモンドがいなかったら、今頃、まだカンザスシティに居るだろう。それも生きていればだが。そうでなければ、ニューヨークでどこかのバンドに入るのに四苦八苦しているだろう。そして、いつクビになりゃしないかと心配しているだろうね。
ベイシーは寡黙と同時に謙虚であることでも知られており、この言葉は正直なものだろう。
ジョン・ハモンドは1930年代から1980年代まで活躍したレコード・プロデューサーで、数々の才能を発掘した。ジョン・ハモンドのおかげで世に出たミュージシャンでめぼしいところを挙げると、ベニー・グッドマン、チャーリー・クリスチャン、ビリー・ホリディ、カウント・ベイシー、テディ・ウィルソンに加えて、ピート・シーガー、ボブ・ディラン、レナード・コーエン、ブルース・スプリングスティーンとフォークやロックのジャンルまで及んでいる。ハモンドによれば、ベイシーバンドの演奏をラジオで偶々耳にし、すぐ世に出そうと考えたそうだ。では、ハモンドはベイシーのどのようなところに魅力を感じたのだろうか。
前に登場したハリー・エディソンによれば、
昔も今もベイシーはテンポ設定の名手だ。ちょうど良いテンポに出会うまでピアノを弄っていて、ちょうどウィスキーを作るのに麦芽汁と酵母を混ぜるのに何回も味見を繰り返すようなもので、フレディ・グリーンとジョー・ジョーンズがそれをフォローする。そして、これだというテンポに出会えば、それでスタートし、フレディとジョーがそのテンポを刻み続けるのだ。
ベイシーのプレイのカギは「テンポ」にあるわけだ。ベイシーはオクラホマのタルサでこれを見付けた。「安定して、それでいてフレキシブル、大陸横断鉄道の機関車のようにドライブするカンザスシティの4/4拍子のリズム」はベーシストのウォルター・ペイジが率いるブルー・デヴィルス(Walter Page’s Blue Devils)から始まったと言われ、力強く疾走しながら同時にリラックスした軽快なリズムはベイシーのバンドの肝となった。ウォルター・ペイジ、ドラマーのジョー・ジョーンズ、ギタリストのフレディ・グリーン、そしてベイシーの4人はオール・アメリカン・リズム・セクションと称された。(二代目オール・アメリカン・リズム・セクションは、マイルズクインテットのポール・チェンバース、“フィリー”ジョー・ジョーンズ、レッド・ガーランド)
テンポが決まると、次にベイシーがやることは、トロンポーン奏者のディッキー・ウェルズ(Dicky Wells)によると、
サックスセクションのテンポを決め、そしてトロンボーンの順となり、我々(トロンボーン奏者)はそのテンポでプレイを始める。サックスのリズムにトロンボーンのリズムをぶつけるわけだ。三番目のリズムはトランペットのものとなる。アンサンブルの間にソロが挟まるわけだが、演奏の始まりはこのようなものだ。ベイシーはこうして曲を組み立てるのさ。
大西洋の荒波のように聴衆に襲い掛かるアンサンブルのリフは少なくとも初めのころは演奏スタイルの売りでもそれが目的でもなかった。ベイシーのバンドは基本的にクリエーティブなソロイストのバンドであり、アンサンブルは二の次だった。ベイシーのミニマリストアレンジの秘密は目立たないことにあり、その目的は演奏をプッシュして前に進めることだ。
結果的にというか、必然的にベイシーのバンドは優れたソロイストのバンドとなり、1930年代から40年代にかけては、オール・アメリカン・リズム・セクションに加えて、テナーのハーシェル・エバンズ、レスター・ヤング、アルトのアール・ウォーレン、トランペットのバック・クレイトン、ハリー・エディソン、トロンボーンのベニー・モートン、ディッキー・ウエルズ、アレンジャー兼ギタリストのエディー・ダーハム、そしてシンガーのジミー・ラッシングというジャズの歴史になお残すプレイヤーが在籍した。
カウント・ベイシーは寡黙だったが、己のアイデアを他の人間に語らせることに長けていた。
饒舌で、前に前に出てくるデューク・エリントンとは全く違ったタイプだが、間違いなく優れたバンドリーダーだった。このことは残された録音に耳を傾ければ一目瞭然だ。デューク・エリントンについては、ホブズボームが辛辣な(”He must also be one of the least likable.”)、一方で、愛情がないとは言えないスケッチを残しているので、いずれ紹介したい。
カウント・ベイシーの全盛期は二度あって、最初は1930年代半ばから40年代半ばにかけて、二度目は1950年代から60年代にかけてで、第一期を「オールド・ベイシー」、第二期を「ニュー・ベイシー」と呼ぶらしい。
上に挙げた名プレイヤーたちを擁していた時期、「オールド・ベイシー」の録音はデッカとコロンビアに数多く残っているので、いくつか挙げてみよう。
このころのベイシーバンドは確かにアレンジというものがあまりなく、特にデッカ盤では、トリオ演奏かなと思ってしまうくらいシンプルなベイシーのピアノとリズムセクションで始まるものが多い。また、ベイシーとリズムセクションのみの録音もある。How Long Blues(1938)はそのうちの一曲だ。ベイシーの訥々としたピアノスタイルも面白いが、叩きすぎない名手、ジョー・ジョーンズのブラッシュワーク、ウォーキングベースの創始者、ウォルター・ペイジのベース、ステディなフレディ・グリーンのギターが十分に聴ける。
ベイシーの伝記のタイトルにもなっているGood Morning Blues(1939年)を聴いてもらうと、さらにベイシーのピアノそして特にジョー・ジョーンズのブラッシュ、シンバルワークの妙がわかる。当初“Count and Lester”のタイトルで発売予定だったRoseland Shuffle(1937年)は「スモールコンボ感のあるビッグバンド」と言われたベイシーバンドの面目躍如で、当初のタイトル通りレスターとベイシーの対話が聴ける。Swinging The Blues(1938年)、Doggin’ Around(1938年)ではスウィングするバンド、卓越したソロイストの魅力が詰まっている。ハーシェル・エバンズ、レスター、バック・クレイトンのソロもいいが、やはり、ジョー・ジョーンズがリードするリズムセクションは一味違う。同時期のデューク・エリントンにも名演が多いが、天才ベーシスト、ジミー・ブラントンがいても、リズムセクションではベイシーに敵わない。
このころのベイシーで、Jumpin’ At The Woodside(1938年)は外せない。オールド・ベイシー時代の大ヒット曲である。バンドが一丸となってドライブしている。バラード曲Blue And Sentimentalもいいが、これは前にレスターについて書いた時に紹介した。
録音が悪くてどうもという声があるが、これで録音が良かったら、どうなってしまうのか。贅沢を言ってはいけない。
コロンビア系列の録音は1939年から40年初頭にかけてのもので、レスター・ヤングがフィーチャーされることが多いので、レスター・ヤングメモリアルアルバムに数多く収録されている。この中で、私が好きなのはまずSong of The Islands(1939年)だ。元がハワイアンなこともあってリラックスした演奏で、ベイシー、バック・クレイトンもいいが、レスターの短いが印象的なフレーズのテナーも聴きものだ。私はこのソロを聴いてレスターが好きになった。レスターのソロで選ぶなら、他に、冒頭からレスターのソロ、そしてディッキー・ウエルズのソロが聴けるTaxi War Dance(1939年)、スイング感がいいRiff Interlude(1939年)、これぞレスターのソロを楽しめるI Never Knew(1939年)、Easy Does It(1940)、そしてBroadway(1940)を特に好きな演奏として挙げたい。
カウント・ベイシーは既に亡くなってしまったが(1984年4月26日)、こうした名演奏を残してくれた。これらの演奏に耳を傾けるだけでなく、もっと数多くの人に聴いてもらうようささやかでも努力しなければいけない。


そうだったのか。
そうだったのかとはなんですかい?
ここはQ&Aが可能です。
次いで、デューク・エリントンについても書いているから、読んでください。