『ヘンリー・アダムズの教育』(1)
The Education of Henry Adamsという本を最近知った。最近出版されたものではない。なにしろ、著者のヘンリー・アダムズ(Henry Brooks Adams)は1838年生まれだ。 この本の存在を知ったのは雑誌『Monkey』(Vol.26)で、編集・翻訳者の柴田元幸氏が、まだ訳すことができない一冊として、「とにかくおかしい本なのだが、どこが可笑しいんだよ、と言われたら…」と紹介していたからで、早速調べると、出てくるわ、出てくるわ、ハードカバーからKindleヴァージョン、表紙も髪の毛豊かな若々しい姿(ハーバード大の卒業写真)から禿頭に髭のオヤジ姿まで、なかにはEnglish to Manx thesaurus(英語からゲール語の一種マン島語のシソーラス)付のものまであり、知らないのはおのればかりで、世の中には読むべき本がまだまだあるものだと感心した。先日も、スティーブンソン(R.L. Stevenson)のKidnapped(『誘拐されて』)は知っていたが、手に取ることもなく常に通り過ぎていたのを、たまたま他にめぼしい本がなかったので、買って読んだのだが、これが面白く、スコットランド・ゲール語に難儀しながらも続編のCatrionaまで読んでしまった。スティーブンソンと言えば、『ジキル博士とハイド氏』と『宝島』が代表作として挙げられるが、上記の本を含めて幅広く読まないと、その真価はわからない。
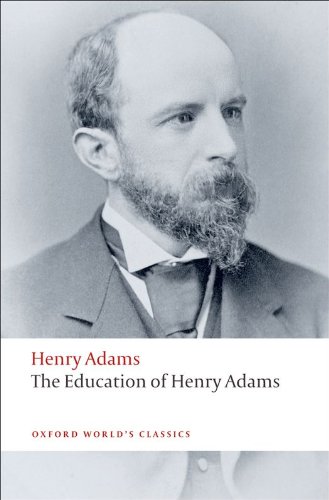
(Oxford World’s Classics)
『教育』に戻るが、数ある版の中から、編集に定評があり、価格が手ごろなOxford World’s Classicsのものを入手して読んでみた。イントロや注を除けば、実質400頁くらいだが、中身は濃く、腰を据えて読むべきものだが、ペーパーバックなので、寝転がっても読めるのはありがたい。ヘンリー・アダムズがこの本を書いた動機には、他人に自分の伝記を書かれる前に自ら書いておこうと思ったとある。特徴は三人称で書かれていることで、自分のことを「ヘンリー・アダムズ」あるいは「彼」と称する時もある。この本は『ヘンリー・アダムズの教育』との日本語タイトルで知られているが、educationには、能力などの育成、養成、さらには教養の意味があり、本の内容を考えると、「ヘンリー・アダムズの学び」あるいは「修養」とした方が良いかもしれない。もしくは、三人称で書かれていることを生かして、「ヘンリー・アダムズを教育する」としても良いかもしれない。
政治史家ホフスタッター(Richard Hofstadter)が『アメリカの反知性主義』の中で、この本を「自己憐憫アートのあの傑作」(that masterpiece in the artistry of self-pity)と言っていた。『アメリカの反知性主義』をペラペラとめくっていたときにヘンリー・アダムズが登場していたのだ。今読み返してみると、ヘンリー・アダムズは反知性の波に抗う知性を代表する米国人の一人として取り上げられているのである。
さて、ヘンリー・アダムズが何者かと言えば、曽祖父はジョージ・ワシントンに次ぐ第2代米国大統領、ジョン・アダムズ、祖父は第6代米国大統領、ジョン・クィンシー・アダムズ、米国南北戦争当時に駐英公使を務め、歴史家でもあるチャールズ・フランシス・アダムズが父親、そして弟は歴史家・批評家のブルックス・アダムズ、母親の家系はボストンでトップクラスの金持ちブルックス家、米国に名門というものがあるならば、まさに名門中の名門に生まれた「坊ちゃん」で、いわゆるブラーミン(brahmin、ニュー・イングランド地方の旧家出のインテリ)の典型と言えるだろう。
米国革命前思想史家モーゼス・コイト・タイラーの、「その始まりからニュー・イングランドは農業主体のコミュニティではなく、工業コミュニティでも、商取引のコミュニティでもなかった。それは考えるコミュニティであったのだ。アイデアの舞台であり、取引の場所でもあった。ニュー・イングランドを何かに喩えるなら、それは手ではなく、心臓でもなく、ポケットでもなく、脳なのである。」を引用して、ホフスタッターは、米国に渡った清教徒の40ないしは50世帯に一人はケンブリッジあるいはオックスフォードで教育を受け、特に聖職者には高い教養が求められたため、植民地時代を通じてその9割以上は大学の学位を持っており、読み書きを重視する伝統とこのようなリーダーに導かれて積み上げられた知的、学問的伝統によってその後3世紀にわたってニュー・イングランドは米国の教育および学問をリードし続けたと述べている。
余談だが、現在、ニュー・イングランド地方のマサチューセッツ州には総合大学、リベラル・アーツ、芸術大学などが63校あるが、そのうち55校が難関校で、「非常に・最も難しい」とされるのは25校もある。ちなみに、「最も難しい」のは、アマースト・カレッジ(新島襄、内村鑑三が出ている)、ウィリアムズ・カレッジ、ウェルズリー・カレッジ(女子大、卒業生にはヒラリー・クリントン)、タフツ大学(村上春樹が講義を行っていた)、ハーバード大学、ブランダイス大学、マサチューセッツ工科大学など、7校もある。昔も現在も高い教育環境を維持しているわけだ。ヘンリー・アダムズはハーバード大卒だが、当時のハーバード大学は、彼には少々物足りなかったようで、「4年間いたが、内容的には4ヶ月あればこと足りるものだった。」などと言っている。しかし、当時のハーバード大は今ほどではなくても、アダムズががっかりするほどレベルが低かったわけではない。アダムズが求める「教育」とは知識を詰め込むものではなく、観察し、経験し、分析することで己の知性を磨くことだから、その点で物足りなかったに違いない。知性と知能の違いについて述べたものがあるので、紹介する。
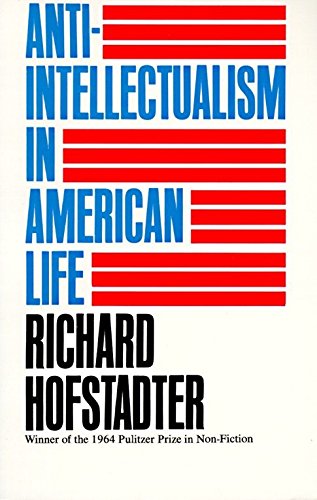
R.Hofstadter
「知能(intelligence)とは極めて限られた、直接的な、そして十分に予測可能な範囲で用いられる心の働きで、その特性は、操作的で、間違いなく実用的なものであり、動物の持つ能力の中では最も抜きんでたもので、かつ持続的なものである。
一方、知性(intellect)は、批判的、創造的、観想的な心の側面であり、知能が把握し、操作し、再整理し、調整することを求めるのに対し、知性は、調べ、思案し、疑義を抱き、理論をたて、批判し、想像する。知能はある状況の直接的な意味を把握し、評価するのに対し、知性は評価を再評価し、状況全体の意味を追求する。知能は動物にも認められ、称賛されるものだが、知性は人間尊厳のユニークな表明であり、人間が持つ特質として称賛され、あるいは非難されることもある。このように定義することで、紛れもなく鋭い知能を持つ人間が非知性的と言われることがあり、さらには、明らかに知性的な心が極めて広範な知能の持ち主であることを理解しやすくなる。」(R.ホフスタッター 『アメリカの反知性主義』)ヘンリー・アダムズがハーバード時代に南部出身の学生についてかなり辛辣なことを言っているが、これは何よりも知性を重視した人間のそうでないものに対する(反知性)に嫌悪の表現だと言ってよい。「厳密に言えば、南部の人間に知性はない。感情はある。学問には向いていない。知性を養う訓練を受けていないのだ。アイデアを子細に検討することもできない。」加えて、ヘンリー・アダムズは、曾祖母であり、徹底的な奴隷制廃止論者だったアビゲイル・アダムズの影響を受けており、奴隷制度の維持を主張する南部に対してネガティブな感情を抱いていた。
また、ヘンリー・アダムズが誕生した19世紀半ばの合衆国と言えば、独立から半世紀以上経過しながら、独立当時から初代大統領、ジョージ・ワシントンが国の崩壊に繋がると恐れていた党派の対立がさらに激化していた。この対立は南部と北部の黒人奴隷解放をめぐる争いと捉えられがちだが、実際はもっと複雑だった。独立直後に勃発した最初の対立は革命戦争の債務処理を巡るもので、次はフランス革命の余波で、フランス革命を支持するグループ(第3代大統領トマス・ジェファーソン、)と英国の王制にシンパシーを感じるグループ(初代財務長官アレグザンダー・ハミルトン、第2代大統領ジョン・アダムズ)の間に対立が生じ、この結果、ジェファーソンおよびジェームズ・マディソン(第4代大統領)が率いる民主共和党(Democratic Republican、現在の共和党と区別するためリパブリカン党とも表記される)が生まれ、また、ハミルトンのグループは自らを連邦党(Federalists)と称した。ワシントンは、「我々に党派はいらない」としたが、様々な政治的主張が対立すれば、党派が生まれるのは避けられない。連邦党が親英的なのは、英国王室が好きだからと言う理由ではなく(多少はあっただろうが)、商業が発達したニュー・イングランド地方に多くの支持者を持つ連邦党として、産業の発展のために英国との関係が重要だと見做したからである。一方で、民主共和党は、「大きな政府」に危惧を抱き、農民や農園主こそが民主的な国家を支える柱だと考えており、連邦党を、自営農民と大地主の犠牲において、都市商工業者の利益をはかるものと見なしていた。経済基盤を巡る議論に加え、国家はどのようなものであるべきかについても大きな意見の対立があり、連邦党は、憲法と強力な中央政府による統一的な国家の建設を目指し、民主共和党は州の独立性と中央政府の権限を制限することを求めた。ざっくりと言えば、両者の対立は民主主義における共和主義と自由主義の主張間の対立というべきで、この対立は根深く、今も続いている。ヘンリー・アダムズは、フェデラリストであるジョン・アダムズの曾孫であり、エリートによる統治を理想としていたジョン・クィンシー・アダムズの孫なので、彼の政治観は当然その影響を受けている。
(2)につづく

