『人工知能と経済の未来』を読んで 1~ 人工知能と人間に仕事について
以下の文章は、井上智洋著『人工知能と経済の未来 』(文春新書 2016/7/19)を読み、その内容をシニア社会学会濱口研究会で話し合うために用意したものである。
「人工知能論」
人工知能(AI)そのものについて仔細に語る知識も見識もないが、養老孟司先生の言葉を借りてまとめるなら、「人間とAIは全くの別物」(養老孟司『AI「無脳論」』文藝春秋2019年三月特別号)で、「AIが人間の脳を本質的に超えることはない」、一方で、AIが「人間の存在を大きく規定していくことは間違いない」ということになるだろう。
「人間の存在を大きく規定していく」と言っても、とりとめがないので、ここでは、『人工知能と経済の未来』のテーマでもある、AIが人間の仕事をどのように規定していくかを考えてみたい。とは言え、現実の世界では、AIそのものが人間とはどうあるべきか、人間にとって仕事はどうあるべきかを規定することはありえないので、人間がAIを使うことで人間の仕事がどのように変容するかということになるが、
グローバルキャピタリズムの下にあっては、競争優位、生産性向上、効率アップの名のもとにその逆になりかねない危険性がある。また、AIを巡る2つの危険な争いに(国家覇権、企業覇権争い)巻き込まれる恐れもあり、また、人間中心と言っても、急速に進むAI技術任せでは、いつどこで方向が狂うかもわからず、ここらで「AIによって我々は何を実現するのか」、ポジティブで明確な目的と目的達成のための道筋を定める必要があるだろう。私には、その道筋は何かを示すことができないので、そのために行われるべき議論のいくつかのポイントを記すにとどめたい。
最近、EUを中心にAIの無制限な開発競争に警鐘を鳴らし、主に倫理的な側面から開発の方向性を定めようとする動きがある。日本もこれに積極的な姿勢を示しているが、これはバイオテクノロジーの分野同様にあくまで倫理面の話で、国際的な取り決めが生活に密着した人の仕事の領域まで踏み込んでくることはないだろうし、AIの時代にあって我々の仕事がどうあるべきかについては、それぞれの国の産業構造や仕事観などを踏まえながら別個に議論されるべきものだと思う。
「AIは人間の仕事を奪うのか、仕事の変化を促すのか」
『人工知能と経済の未来』の著者は、人工知能(AI)によって「多くの労働者が機械に仕事を奪われ」ることで多くの人間の仕事が代替され、「仕事がなくなる」ことを論じているが、まず考えるべきは、仕事がなくなる、なくならないではなく、AIによって人間の仕事およびその仕方がどのように変容するか、まずその可能性を探ることではないだろうか。
AIによって人間の仕事がどのように変化するかはもちろん仮定の域を出ないが、一つの考え方を引用させていただく。
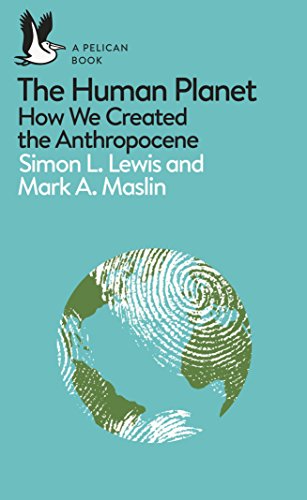
The Human Planet
「情報生成力とコンピュータープログラムが進歩するということは、人間の行う仕事がさらに自動化されることを意味し、肉体を使う仕事はロボットに、頭を使う仕事はコンピューターによって行われるようになる。つまり、自動化とは、人間にとって退屈かつ不快な仕事が、賢くプログラムされ巧みに設計されたロボットによってこなされることなのだ。これによって人間は骨折り仕事から解放される。」(S.L. Lewis、M.A. Maslin The Human Planet Pelican Books、2018)
人間の仕事には機械やコンピューターに代替させても良いものがあり、それは人間にとって退屈かつ不快な仕事であると述べている。ポジティブな見解だが、「AIを使う」という人間の立場から見れば、このようなことになるのだと思う。
ここで語られている仕事はいわゆる単純肉体的作業が主だと思われるが、一歩進んで、それ以外にも代替されてよい仕事(なくなってもよい)があるようだ。

社会人類学者のデヴィッド・グレーバー(『負債論』などの著書がある)はその著書『どうでもいい仕事』で、20世紀半ばから急速に拡大している情報・通信業(Information Industry)の中に数多く含まれる「どうでもいい仕事(Bullshit jobs)」に分類されるものとして、「全く無意味で、必要性がなく、あるいは有害であり、雇用者側がそうしたくてもその存在を正当化できない雇用形態」があることを指摘し、世の中の仕事の過半数は無意味であるとした上で、特に、次に挙げる5つの仕事は全く意味がないと断じている。
①Flunkies(取り巻き、おべっか系):利用者(雇用者)が重要な人物だと思わせるために存在する仕事
②Goons(用心棒系):雇い主のために相手を攻撃する仕事③Duct-Tapers(修繕屋系):出来の悪いプログラムの修正など、不備のために発生する、そもそもあってはならない問題の手直しをする仕事
④Box-Tickers(社内官僚系):基本的に内側だけを向いている仕事
⑤Taskmasters(仕事作り屋系):無駄な業務を生みだす仕事
(D. Graeber Bullshit Jobs Simon & Schuster、2018)
グレーバーはそれぞれについて具体的に仕事を挙げているが、仕事や職種については文化の違いもあり、はてなと思うところもあるので割愛する。これらの仕事は、テクノロジーの進化がむしろ無意味な仕事を作り出す方向に使われた結果であるとも述べている。
20世紀半ばから(米国では1950年代を境に)金融サービス、マーケティングなどの新しい情報関連産業、さらに企業法務、人事、広報といった管理系のホワイトカラーの仕事が急激に増えている。グレーバーによれば、ロビイスト、企業顧問弁護士などの高収入の仕事はなくなってもさほど困らず、むしろ社会が良くなるかも知れない類の仕事だが、まるで誰かが意図的に、人を働き続けさせるためだけに無意味な仕事を作り出したかのようであり、何より問題なのは、こうした仕事はやっている本人自身がその有意性に疑問を抱いていることで、一方で、看護師、保育士、公共交通機関の運転手など直接的に社会に貢献している人々ほど賃金が低く、社会的な立場は不安定である。しかも、このおかしな状況についてこれまで公に議論されることもなかったとグレーバーは指摘し、その仕事がいかに無意味でも(無意味と感じても)、規律を守って長時間働くこと自体が自らを価値づけるとの現代の労働倫理観は、労働には宗教的な意味があるとのピューリタンの倫理に由来する(マックス・ヴェーバー)と考え、この精神的束縛は、現代人の「潜在意識の奥底に組み込まれた暴力」であると述べている。
いずれにせよ、現代社会の仕事・労働観にこのような歪みがあり、それが社会問題(最近ではバイトテロなど)の一つの原因となっているとしたら、その解決を図らずに、AIの急速な発展のみに頼る社会では歪みがさらに悪化し、それの社会は「ユートピア」ではなく、イスラエルの歴史学者(ユバル・ノア・ハラリ『ホモ・デウス』2015年)が指摘するように歪みを放置ないしは利用する一握りの人間のみが恩恵を得る「デストピア」となる可能性もあるのではないか。
(2~人工知能と人間の共生としてのThird Place に続く)

