『君たちはどう生きるか』を再読する~透けて見える時代性~(1)
『君たちはどう生きるか』を読んだ方々は、「生き方を教えてくれる」、「清々しい読後感」、「現在でも色あせない内容」などきわめてポジティブに評価している。
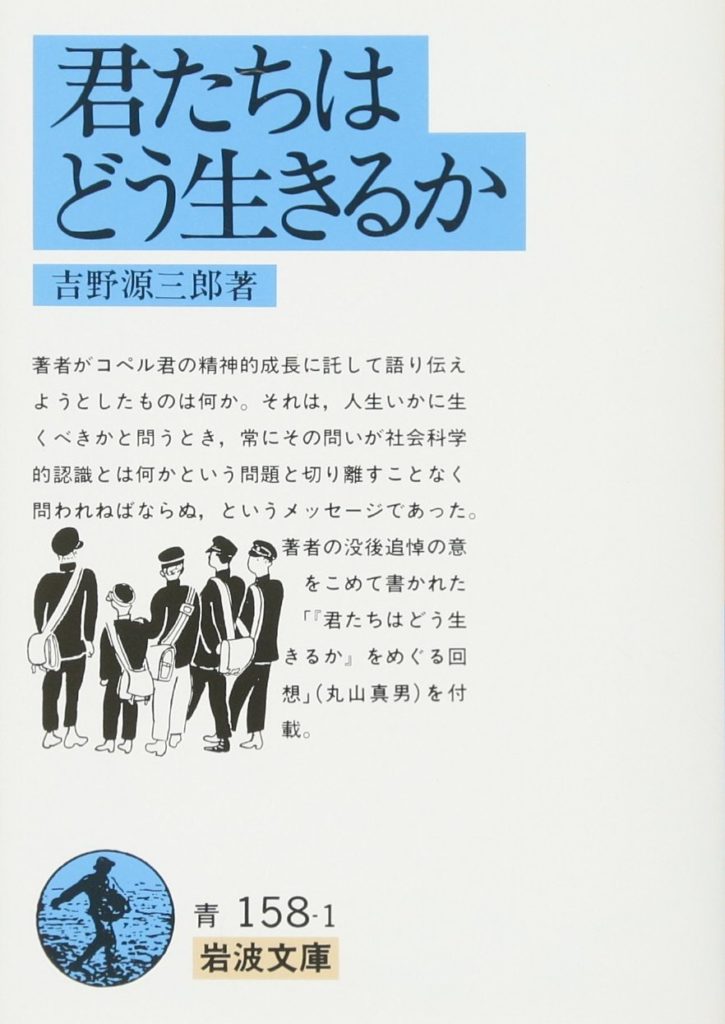
私もかなり前に岩波文庫の本書を手に取って読んだときは世評通りの本だと感じた。しかし、今回、読み直してみて、なるほどとは思ったが、違和感もあった。実はこの違和感は最初に読んだ時にもあったのだが、こうした「良い話」に常に抵抗感を覚える質のせいだろうと思ったのだ。この本は、戦前の1937年に『日本少国民文庫』の一冊として出版された「少年のための倫理の本」であり、純粋な少年少女(とは言え、少女たちを読者層と見做していたかは疑問)のために書かれた本に本来の読者層から外れたオヤジがあれこれ言うのもどうかとは思うが、現在、この本の読者の多くが大人であることを考えれば(岩波書店も老眼の大人用に「ワイド版」を出している)、大人の一人としてどのように読み、感じたかを語ることは意味のないことではないと思う。
今回あらためて感じたその違和感は以下の三点に集約でき、これらは著者の考え方と言うより最初に書かれ出版された当時の時代的なものを反映したために生じたものではないかと考えている。
①「選良意識」と社会階層間の差が厳然として存在した戦前のモノの観方が反映されていること
②コペル君が始めから終わりまで行動しない「傍観者」であり、基本的に叔父さんの意見によって動かされている存在であるために、その「発見」と「成長」に実感が乏しいこと
③「世界は自分中心に回っていない」人間分子の法則と言う気づきがありながら、「自分がいい人間になる」との自己中心的な倫理観に落ち着いてしまうこと
①「選良意識」と前時代的な社会構造の戦前のモノの観方が反映されていること
この本を読んでまず感じたのはこの点だ。前時代的な家柄という価値観が残り、それに学歴が加わった戦前の昭和の社会構造は緩やかであっても基本的に身分社会で、この本にもその社会構造が反映されていると感じさせ、今の時代にいる私には相当な違和感があった。この点についてはどなたもそう感じるのではないかと思うのだが、どうだろうか。し
■「あの人々」とはだれか
エリート層や金持ちの子弟ばかりの登場人物の中にあって唯一の貧乏人であり異色な存在である浦川君は、「背は中ぐらい、恐ろしく胴長で、服はだぶだぶで一向体にあっていない、帽子だけは、バカに小さいのを、兵隊のように真直ぐにかぶって、運動神経がどうにかしてて、間の抜けたモーションはどう見ても漫画としか思われない」。学業の方も「あまりよい出来ではなく、教室で居眠りすることにかけては、クラスでも評判の大家」、「すべてが貧乏臭く、田舎染みている」、「浦川君の育ちは、どうしても争えない」と描写されている(富裕な家庭に育つ水谷君は対照的に「体つきもすらりとして、顔も美しく、態度がいつももの静かで、どこか少女のように内気な」と描かれている)。最初にこれを読んだ時、書かれた当時の時代相を差し引いても、貧乏人浦川君に関する著者の描写は容赦がなく、おもしろおかしい調子が浦川君を小ばかにしているとの感じをさらに強めていると感じた。著者は「馬鹿にされてもしょうがない」貧乏人の倅として浦川君を描いているのだ。しかし、実際の浦川君はこのような見かけから想像するような人物ではない。彼は、自分がいじめられるときは耐え、他人に危害が及ぶようなときは身をもってかばう強い精神力と行動力を持っているのだ。貧乏だからこうなるのだという先入観を排して浦川君を描けばこうなるだろう。「背は中くらいだが、服は大きめ、帽子は小さめで、どちらも体にまったく合っていない。運動神経はお世辞にも良いとは言えない。いつも疲れているためか、授業では居眠りすることも多い。英語や数学の成績は良いとはとても言えないが、漢文の成績はクラスの連中がいくら勉強しても追いつけないほど優れているのだ」。
著者の貧乏に対する考えは「貧すれば鈍する」で、貧しいと見かけも態度も劣化するのだ。繰り返すが、浦川君は劣化してはいない。
こうした著者の考えは当然ながら叔父さんのものの見方に反映されている。
「浦川君のような人は、まわりの人が寛大な目で見てあげなくてはいけないんだ」と叔父さんが言う浦川君は誰からも寛大な目で見てもらう必要がない存在だ。本の冒頭近くにあったエピソードで喧嘩を必死に止める姿を見れば意気地がないとの評価も間違っている。
浦川君のエピソードを受けて、叔父さんがしたためた「人間であるからには‐貧乏ということについて‐」という手紙の中に表れた叔父さんの考えをまとめると、
- 世の中の大多数の人々が人間らしい暮らしができていない貧乏な人だ
- 貧乏人はたいてい自分が貧乏なことに引け目を感じながら生きている
- 自尊心をもっている人間でも貧乏な暮らしに引け目を感じるのは免れがたい人情
- 貧しいことに引け目を感じるようなうちは、まだまだ人間としてダメ
- 貧乏人に対しては、傷つきやすい自尊心を心なく傷つけるようなことをしてはいけない
つまり、貧乏人が自分の境遇に引け目を感じるのは人情として当然だが、引け目を感じて当然な貧乏人がそれでも引け目を感じるのは人間としてダメだと言っているのだ。世の中の大多数の貧乏人のそのまた大多数を否定しているわけだ。このように決めつけておいて、最後にこうした人たちなのだから、優しく接しなさいと言う。まったくの「上から目線」ではないか。
さらに叔父さんは、コペル君が思いついた「人間分子の関係、網目の法則」について、人間同士は「切っても切れない網目で、お互いにつなぎあわされて生きている」と論じたうえで、「中学以上でなければ教えられない事柄については、ごく簡単な知識さえもっていないのが普通」であり、「ものの好みも、下品な場合が少なくない...あの人々こそ...立派なひとたちなんだ」と「あの人々」(つまり、無学で下品な好みの貧乏人)を持ち上げている。
その理由は、「世の中の人が生きていくために必要なものは、どれ一つとして、人間の労働の産物でないものはない」、「学芸だの、芸術だのという高尚な仕事だって、そのために必要なものは、すべてあの人々が額に汗して作り出したものだ」、「あの人々のあの労働なしには、文明も世の中の進歩もありはしない」からだ。世の中は「生産する人」と「消費する人」で成り立ち、生み出していく人(生産者)は、それを受け取る人々より、はるかに肝心な存在だからだ。ここで問題なのは「生産する人々=貧乏な人々」の図式で、日本の経済が零細な工場や安い賃金で働く労働力の上に成り立っていた時代を反映しているわけだ。
さらに問題なのは、こうしたステレオタイプ化した考えを「生産と消費」の仕組み理解に容易に持ち込んでいるところだ。さらに、何回も繰り返される「あの人々」という言葉に違和感を覚えないだろうか。ここには「われわれ」とは違う場所にいる人々に対する差別意識がある。叔父さんそしてコペル君と「あの人々」との間には大きな溝があるのだ。叔父さんは、消費者でしかないコペル君が生産者である貧乏人の上に胡坐をかいてはいけないと語るが、子どもは当然生産者ではないわけで当たり前のことであり、この忠告は、「われわれ」社会の中上層部にいる人間はそうであってはならないとのアドバイスなのだ。「われわれ」と「あの人々」に別けることは、この本の重要な「ものの見方」である人間分子同士の調和ではあってはならないことなのだが。
■エリート予備軍に対するメッセージ
この本が書かれた当時の社会階層のギャップを反映しているのはやむを得ないとしても、叔父さんのものの考え方に根強い階級区別の(差別とは言わないまでも)意識があるのはいただけない。
「貧乏人の傷つきやすい自尊心を傷つけるな」と言う叔父さんにはいわゆる「ノブレス・オブリージュ」意識があるように思える。ノブレス・オブリージュとは、特権は、それを持たない人々への義務によって釣り合いが保たれるべきだという「モラル・エコノミー」を要約する際に、しばしば用いられ、主に富裕層、有名人、権力者、高学歴者が「社会の模範となるように振る舞うべきだ」という社会的責任に関して用いられる言葉だ。
叔父さんが(コペル君の亡父である兄の意を受けて)コペル君に授けているのは支配階層のあるいは社会のエリート層の「帝王学」ではないかとさえ思える。また、これは著者の想定読者層であるエリート予備軍の少年たちへのメッセージであったのかもしれない。
(2)へつづく

