コロナ感染拡大防止策として人の移動の自由を制限すること(7)
《エンパシーと積極的自由》
実は、エンパシーは人権思想の受容と浸透にかなり大きな影響を与えている。人間の共感能力(エンパシー)の高まりがなければ、人権思想は啓蒙思想の枠を出ず、エリート・特権階級のきわめて個人的な権利意識に留まり、地域を超えて広く共有されることなく、思想として大きな力になることはなかっただろう。つまり、それが造物主によって与えられたものであるかの議論はともかく、単に人間であるということに基づいて人間には普遍的権利があるとするきわめて抽象的な人権意識は、自分と同じ権利が他人にもあるとの実感がなければ成立しにくい。他者にあるから自分にもある、あるいは自分にあるものが他者にもある、権利があまねく共有されているとの意識が力になるのであって、この意識が広く根付いていないと、人権は「おおげさなナンセンスnonsense upon stilts(自然権としての人権は実証不可能であるから、まともな論議ができない。その意味でナンセンスでしかないの意)」(J.ベンサム)となり、政府ないしは権力者によって与えられ、保証される権利にすぎず、権力者や政府の意向によって左右されるきわめて危ういものになってしまう。
他者の権利を自分と同じように認める能力、つまり、他者に感情移入する、共感する力が人々に備わっていること、すなわちエンパシーが備わっていることが人権の地盤を確固なものとするために必要なわけだ。
しかし、近年の研究では、共感能力は人類を他の霊長類を含む動物と区別する重要な能力であり、人権思想が生まれるはるか前から人間が備えているものだと判明している。「人間とは何か、という学問領域を越えた普遍的問いに対して、共感性(empathetic system)の理解が不可欠である....ヒトが有する心的特性で他の生物と決定的に異なる特性は、血縁者のみならず非血縁者と共に、きわめて高度で複雑で大規模な協力的社会を構築し、見ず知らずの他者に対してさえ向社会的に振舞う点にある」(長谷川寿一『共感性研究の意義と課題』2015)
血縁的、地縁的な人々など自分の身近な人間たちに共感するのは自然なことであり、たやすいことだ。しかし、それ以上に、共感の対象である他者の範囲が地縁・血縁を超えて見ず知らずの他人まで広がるかが問題なのだ。
近代以前では、洋の東西を問わず、人々は「領民的」思想に閉じ込められていたと自由権のくだりで述べたが、つまり、人民を生産者として自領内に確保する目的で職業や住居が固定されていたわけで、人々同士の接触は地縁血縁の枠を出ることなく、地縁血縁の外の人間関係はきわめて希薄なものだった。加えて、厳格な身分制度があり、身分を超えて人々が接触することもまずなかった。このような状況下では個々の人間や民族などの相違点を越えた《類》としての人間、すなわち「人類」という考えは広く成立しにくい。人類どころか「国民」という概念でさえ成立しがたい。
余談だが、2008年5月12日に勃発した四川大地震は被災者総数460万人強、死者7万人、負傷者38万人、行方不明者2万人に及ぶ関東大地震レベルの大災害だったが、四川の中心である成都から2000キロ、飛行機にして3時間の距離にある上海では、オフィスにおける地震に関する中国人スタッフの会話もさしてなく、街中でも、国内で大災害が起これば当然予想される緊迫した空気が感じられなかった。ところが、その3年後に発生した東日本大震災では、当時私は上海にいたが、オフィスのみならず行きつけのレストランまで日本の地震が話題になり、その違いに驚いた。自国の四川より異国の日本に対する関心が高いのだ。中国人は地縁血縁関係を重視し、その外にいる人々には無関心だと聞いていたが、それを実感した。2000キロ離れた四川は自国とは言いながら「遠いところ」で、そこで起こった出来事は確かに大事件だが、自分たちの生活に直接影響がなければ大して気にすることはないのだ。中華人民共和国に住む人々は外から見れば一括して「中国人」だが、彼らの意識では上海にルーツがあれば上海人であり、広州ならば、広東人で、北京語を介してのみ広東人と上海人の会話は成立する。
このようにバラバラな国民を中国人民としてまとめるにはシンボルあるいは神話が必要であり、さしずめ、漢族と周辺の少数民族を束ねる民族概念として中国政府が打ち出した「中華民族」がそれにあたる。しかし、実態は漢族優先であり、一方、ウイグル族などの少数民族は無理やり「中華民族」の一員とされて、そのアイデンティティを奪われつつある。同じくバラバラな国家、アメリカ合衆国の神話は「自由」だが、これも国民を統一させるどころか、分断の理由の一つにもなっている。
さて、エンパシーには、他者の情動に同調して同じ感情を持ってしまう情動的共感(affective empathy)と、他者の状態を理解しつつも、自己と他者を分離したうえで、他者に共感する認知的共感(cognitive empathy)の2つがあるとされている。人の心の動きとして情動的共感と認知的共感は分離できないもので、情動的共感力が不足し認知的共感力のみと高いと、人の心を読む能力に長けているが人を思いやる情に欠ける詐欺師やサイコパスに近い存在になってしまう。本来、情と知は切り離せないものなので、広告で時に面白いものがあるのは、専ら面白さを追求したわけではなく、情動的な反応が伴うと記憶されやすいという心のメカニズムを利用したいがためなのだ。しかし、エリマキトカゲのように面白いがなんの広告だったっけというのは残念ながら失敗作だ。
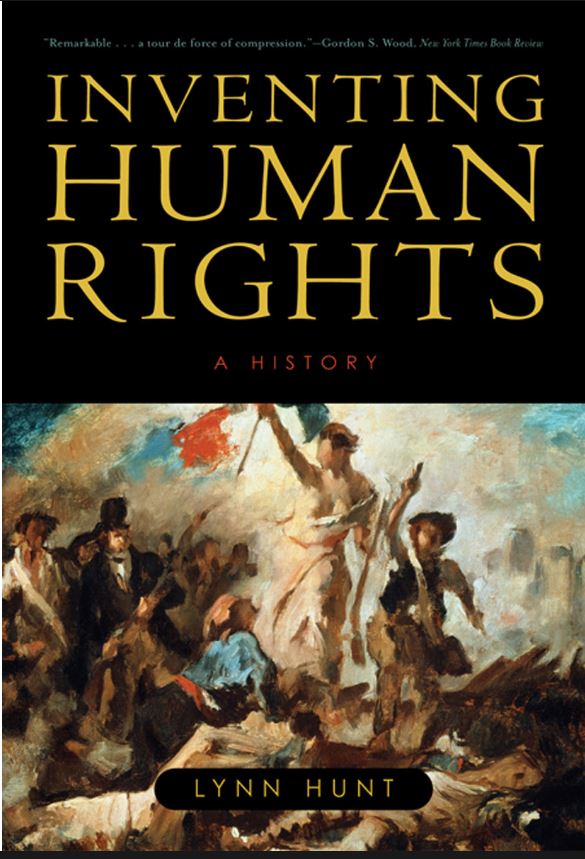
Inventing Human Rights
18世紀から19世紀にかけて欧米を中心にこの情動的および認知的共感能力が高まり、それとともに人権思想が広く受け入れられていくのだが、これに関して米国の歴史学者、リン・ハントがその著書(『Inventing Human Rights』2007年)で詳しく述べているので、紹介したい。
リン・ハントは、アメリカ独立宣言とフランス人権宣言の2つの人間は生まれながらにして等しく権利を有するという思想が18世紀後半に生まれたのはなぜだったのかを調べ、いわゆる人権意識が18世紀後半から19世紀前半にかけて醸成されたのは、一般市民の間で新しい文学形式である小説(特に作者が表に出ない書簡形式のもの)を始め、人間性を謳う芸術が社会に普及したことにより、それまで人々のコミュニケーションで壁となっていた性、年齢、階級、地域などの障壁を乗り越え、他者に共感する力(エンパシー)が高まったからだと述べている。人権の思想が人の考えとして支配的なもののひとつになったのは人間の共感力の高まりに負うところが大なのだ。もちろん、移動の自由の権利を勝ち取り、交通手段が普及、発展し、地域、国を超えた自由な往来が可能となり、新聞など新たなコミュニケーションのためのメディアが普及したことも、共感力醸成に大いに寄与した。つまり、コミュニケーションのコンテンツ(小説など芸術)とメディア(出版物、新聞など)双方の発達が人間の共感力を高め、人権思想を受け入れる下地を作る一因となった。
ここで、今回のコロナウイルスパンデミック感染拡大防止のために行われた移動の自由の制限に戻る。結局、近代から現代へ、王侯貴族の支配する世界から民主主義を謳う社会への道筋には移動、居住の自由が大きな意味を持っていたわけだが、一度自由を手に入れた者がその自由を一時的にせよ手放すことは想像以上に苦痛を伴い、感染拡大が比較的コントロールされているドイツにおいてさえ、政府によるさらなる移動の制限措置、さらにはマスク着用義務に対しても人々の間に強い反発が生じている。民主主義を標榜する国家にとって、コロナウイルス感染防止という大義があっても、人々の自由を長期にわたって制限することはきわめて難しいことがわかった。つまり、人々の接触を制限して感染拡大予防を図ることについては政府ができることに限界があるのだ。しかし、政府には積極的に果たすべき役割がある。ワクチン開発にかかわる調査研究、防疫、検査・診断・治療の医療体制整備、経済的損失の補填、経済刺激策などするべきことは山積している。
米国の政治家(民主党所属)および社会学者で、上院議員を務め、1960年代から80年代の米国の政治に大きな影響力を持ち、ケネディおよびジョンソン政権時代に労働省次官補として「貧困との戦い」と呼ばれた社会福祉政策の立案に携わったダニエル・パトリック・モイニハンは次のように述べている。「民主主義の安定はひとえに、政府ができること、できないことを人々がきちんと区別できるかにかかっている。政府ができることを要求するのは理に適っている。それが実現されることを望む者も、望まない者もいるだろうが、どちらか多い方がそれを決めるだろう。しかし、政府ができないことを求める時、しかも、できるはずだと根拠のない強い思い込みでそれを求める場合は挫折あるいは破滅の状況をもたらす。」経歴からも分かるように、モイニハンは黒人の貧困問題の原因を究明するなど社会科学の知識を実際政治に投与し、また、福祉政策を重視した政治家で、いたずらに小さな政府を目指すリバタリアン的政治家ではない。彼が言いたいことは、行政サービスが「天から降ってくる」状態では、人々は単なる「客体」 と化し、自らを統治する行政や政治の姿を体感できない。人々は「天」に向かって「要求」をエスカレートさせるしかなく、行政ニーズは多様化し、支出は膨れ上がるばかりとなる。経済誌The Economistの記者は今回のコロナで打撃を受けた欧米諸国の状況がこれにあたると指摘している。エスカレートする要求で政府が機能不全に陥っていたところにコロナウイルスが襲来したわけだ。一方で、市民が司法、教育、 福祉といった分野の現場に入り、責任を分担するような社会では、市民は 「調整」の難しさを知り、自治における責任とは何かを体感することができる。
欧米、日本をはじめとする民主主義体制の国家に生きる人々は、自由、権利、安全(「安全」については温暖化による自然災害の増加で、意識に変化が認められるが)は「空気のようにそこに自然にある」ものとみなし、それを提供するのは国家の役割として、自ら果たすべき役割を強く意識せずにきた。多くの人々にとって投票行動が唯一の政治参画だが、それをしない人も多い。今回のコロナウイルス危機は、政府ができること、我々ができることを見直す良い機会となった。
今、日本を含む世界の人々は、コロナウイルス感染拡大防止のために課せられた制約に悩んでいる。欧米では、特にマスク着用の義務化には抵抗がある。マスクは自分が感染しないためのものというより他者に感染させないためのものだという意識が希薄なように見える。この点で東アジアの国々とは対照的だ。欧米の人々は制約から逃れる闘い、つまりfreedom from制約で、いわば消極的自由、他者の権力に従わない状態、他者の強制的干渉が不在の状態を求めているわけだが、他者に感染させないための行動を行う、ある目的のために意思を持って行動する積極的自由、freedom to、の方に意識を転換できないのか疑問に思う。おそらく、エンパシーが足りないに違いない。
ところが、エンパシー、人権思想の逆を行く、人々の間に壁を作る考えがフランス革命後に生まれている。その最たるものがナショナリズムだ。ナショナリズムはフランス革命が生み出した皇帝ナポレオンが没落し、その後に残った荒廃したヨーロッパから生まれた。その中でも最も荒廃し、分裂し、しかもアンチフランスであったドイツにおいて最もフランス的と見做した人権思想が拒絶され、ドイツ民族を他から区別する言葉Volksを強調し、19世紀初頭に、狂信的な愛国主義者フリードリヒ・ヤーン(「体操の父」とも称されている)は「人々は純血であればあるほど良い」とし、現在まで続く災いの種をまいた。今の世界はナショナリズムのみでなく、レイシズム、セクシズムなど様々なIsmが蔓延して、人々の間に高い壁を作っている。コロナウイルスはグローバルに垣根なしに人々を感染させているのに対し、人間はグローバルに協働してコロナと闘えていないのだ。
今回の新型コロナウイルスに関しては、新薬、ワクチンによって感染が抑え込めるかもしれない。しかし、パンデミックはこれで終わりではない。新型コロナウイルスの次がやってくるのはほぼ確実だろう。今回のパンデミックを通じて、感染防止に関しては政府、行政ができることには限界があり、人々が人に感染させないという意識で日常の活動を組み立てないと防止ができないことを知った。人々の心の内にある壁を低くして、人間本来の能力であるエンパシーを働かせなければならない。
我々日本人も人目を気にして自らの行動を律する「自粛」から抜け出して、「人に感染させない」ことを明確に意識して積極的に行動すべきだろう。そうできれば、パンデミックに対してだけでなく、人間が作り出した様々な社会的バリアー乗り越えて、次の道筋が見えてくるかもしれない。
「世間」(よのなかとも読む)とは、 人が集まり、生活している場。自分がそこで日常生活を送っている社会を指し、つまり「場所」のことだが、現代では「空気」と言い換えた方がいいだろう。「空気を読む」ことが生きるためには必要なのだ。空気は場所よりも実態が曖昧だ。曖昧なものに対して行うのが「自粛」だ。行動の規準などはなく、「空気を読みながら」慎むので、自粛によって何がもたらされるのか、その結果も曖昧なのだ。
2020年10月22日 発表

