コロナ感染拡大防止策として人の移動の自由を制限すること(4)
米国におけるコロナ感染拡大防止措置と反応
トランプ大統領が緊急事態宣言を行ったのが3月13日で、ドイツよりも早かった。それから約半年経過しているが、今や米国は感染者数(累計815万人)と死者数(22万人)において他の国を大きく引き離しており、さらに二次の爆発的感染により、12月までに新型コロナによる死者数が32万人に達し、新型コロナはアメリカ人の死因の1位になるとの最新予測もある中で、これほど実効性がない緊急事態宣言も珍しい。ノーガードで選挙活動を行った結果トランプ大統領本人も感染し、ホワイトハウス内部にも集団感染が発生したことを見ても、インフルエンザに比べればコロナウイルスなど大したことはないなどと甘く見ていたトランプ政権の失態は明らかだ。
米国では、感染症対策は連邦政府とは別にそれぞれの州に強い権限があるのが特徴だが、連邦政府の対応が後手後手に回り、国としてまとまった施策が打ち出せず、州レベルの対応の違いばかりが目立つ。米国は、保健衛生の分野で、研究レベルも資金も情報も、世界で群を抜いた能力を持っていると言われているが(CDC米国疾病予防管理センターの存在など)、そうした強い力をこの新型コロナウイルスの危機に生かせないでいる。
トランプ大統領は、感染抑止の対策はそれぞれの州に任せても、米国経済の復興は、あくまでも自分が主導権を握ると主張している。感染抑止策と経済対策は表裏一体の関係にあるはずだが、コロナ対応が遅れた責任は各州にあり、経済復興は自分の成果にしようと目論んでいる。
WHOに対する資金拠出の一時的な停止も、自らへの批判をかわすための責任転嫁の試みだろうし、国際機関を舞台に影響力の拡大をはかる中国をけん制する狙いもあるだろう。
州単位で新型コロナウイルス感染防止策として外出禁止、店舗、レストランの営業制限など様々な私権制限施策を打ち出しているが、特に外出制限に対する抗議デモが全米で発生している。この動きは市民運動に見せかけて展開される組織的な意見の主張ではないかとの疑惑がある。一部メディアは、抗議活動の背後でトランプ政権と関係の深い有力組織が動いていたと指摘し、単純に一般市民の不満が爆発したわけではなく、経済再開を強く求める企業などが陰で扇動していたのではないか、というのだ。だが、ソーシャル・ディスタンシングなどの規制措置の解除を求めて、全米で人々が抗議のために街に繰り出していることは事実だ。他の国々ではこれほどの規模でまたこれほど頻繁に抗議活動が発生しているとの報道はなく、これはきわめて米国的な現象と言えるだろう。ニュースで見る限り、反対デモの参加者はローワーミドルクラスの白人(以前はプアホワイト、現在ではWhite Trashと称される)が主体で、共和党というよりトランプの支持者が多い印象がある。もちろん、ノーマスクがほとんどだ。ということで、コロナウイルス関連で米国国民の特筆すべき反応はやはり「マスクを巡る論争」に尽きるだろう。
先日、フロリダ州パームビーチ郡において、新型コロナウイルスの流行対策として公共の場でのマスク着用を義務化する法案の採決の前に委員会が市民の意見を聞く機会を設けたことがニュースになっていたが、反対を唱える市民からは、マスク義務化は悪魔の法律だという意見や、共産主義の独裁体制だ、米国国旗に対する侮辱だといった意見があり、なかには、「神によって与えられた私の呼吸を奪うな」と大真面目に滔々と訴える女性もいて驚いた。新しいところでは、「新型コロナウイルスの感染拡大防止を求めて、マスク着用を強制させられるのは、ナチスドイツ時代にユダヤ人が黄色いダビデの星を着用させられたことと同じです。マスク着用を強制され、マスクをしていないと罰金が取られたりするようになれば、このマスクは私たちにとっては黄色い星のようなものです。恐ろしい話だと思いませんか?」と発言して炎上した女性もいる。とにかく、ほとんどが確たる理由も根拠もなく自己中心的思い込みで、公聴会で耳を傾ける価値がある意見ではなかった。マスク着用への抵抗は生理的嫌悪感もあるだろうが、それ以上に、「自分の健康は自分で守る」、それが自主独立ということで、マスクの着用強制への拒否感は医療保険への加入を強制されるのが嫌だということと同じ理屈らしい。このようなレベルの発言が意見としてまかり通るのはなぜだろうか。誰でも思ったことを口にできる表現の自由を最大限尊重する「自由の国アメリカ」だからだろうか。
コロナウイルス一次感染本格的拡大時期の日経新聞(5月14日)によるニューヨーク・タイムズ紙の調査では、米国でマスク着用率が高いのはハワイ州の58%で、ニュージャージー(56%)、ニューヨーク(53%)の各州が続き、これらの州では3月から5月12日にかけてコロナの新規感染者数が減少傾向にあった。一方、同時期に新規感染者数が増えたサウスダコタ州はマスク着用率が32%、ミネソタ州は33%と全米で最低水準だった。アラバマ州(38%)やアーカンソー州(39%)も同様に感染者の増加が目立つ。この数字を見て、マスク着用はコロナウイルス感染抑止にかなり寄与していること、米国はマスク着用派とマスク非着用派に2分されていることが分かる。現在では、マスク着用を義務化した州も多いので、マスク着用率はかなり上がっているだろう。しかし、頑として着用を拒む人々も存在するのだ。
トランプ政権が誕生してから分裂がますます顕在化した米国だが、実は建国時から一枚岩ではなく、当初から北部の工業地帯を中心としたフェデラリストと南部の農業地帯を地盤とするリパブリカン党(現在の共和党とはまったく異なる)の対立があり、ジョージ・ワシントンが大統領になったのもこの対立を収めるためで、ワシントン自身出来たばかりの国の分裂を心底恐れていたという。現在でも民主党と共和党の2大政党の基本政策はかなりかけ離れている。また、マスク拒否派がマスク着用強制によって脅かされると主張する「個人の自由」についても2つの異なる考えが米国にはある。「自由は市民が権力との闘いを通じて勝ち得たもので、憲法および様々な制度によって権利として保障されたものである」との考えと、「自由は人間が神から与えられたもので自然に備わっているもの」との考えが拮抗しているのが米国なのだ。前者は進歩的な考えの人々、いわゆるリベラルに支持され、後者は保守層の人々の多くが抱く考えだ。一方で、問題なのは、かなり多くの米国人が、後者の自由の考え方に基づく「個の自由」が米国人のアイデンティティとして「米国人であることは自由なことだ」、さらには「自由でなければ米国人ではない」との固定観念を抱いていることではないか。マスクに強い拒否感を抱く米国人は、「権力によって強制される」ことの嫌悪感に加え、それによって自分の自由が奪われる(と感じる)ことは、すなわち米国人としてのアイデンティティを失うことと同じであると思っているのではないか。これは銃保有の自由を主張する考えと一部重なっていると思う。
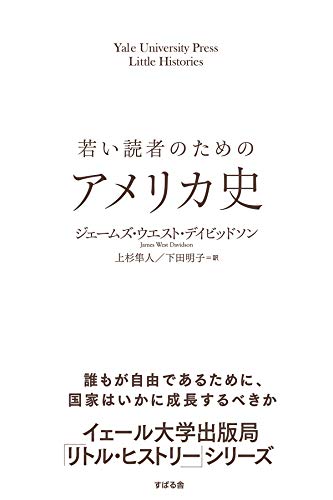
自由が「幾世代にもわたる試練を経ながら、一つまた一つと、具体的な事実関係の中で順次に獲得されてきた集積物である。・・・・そのいずれもが古来より明白な歴史的かつ具体的権利として承認されてきた」(エドマンド・バーク)ものであるとの考えの自由は歴史的事実に照らし合わせて証明可能なものだが、「生まれながらにして自由」は理念で、皮肉な言い方をすればレトリックだ。しかし、造物主から人が与えられた侵すべからざる権利の一つが自由であるとの理念を世界に先立って高らかに宣言しながら、先住民さらには黒人奴隷の自由と権利を認めていなかったのが米国なのだ。独立当初より米国の経済を支えた綿花、煙草、米などの農作物(南部)とそれらを製品化した産業(北部)は、先住民族から収奪した土地の上で過酷な労働を強いられた黒人奴隷によってもたらされたものだ。(この辺のところは『若い読者のためのアメリカ史』(すばる舎)を是非一読されたい。「アメリカ発見」からトランプ以前に至る通史で、手際よくまとめられている)
“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”(米国独立宣言より)
人は米国と聞けば「自由の国」とすぐ連想するが、「平等の国」とはすぐに思い浮かばないだろう。上に引用した独立宣言の文章では、自明なものとして、全ての人間は平等に造られ、とあり、平等は自由に先立つ。また、本来、「自由」と「平等」は一括りの言葉だったはずだが、米国の現実では、この2つの言葉がさらに離れつつあるようだ。
今回のコロナ感染で米国社会の不平等がさらに明らかになった。新型コロナウイルス感染症の感染者数とこれによる死亡者数が世界最多となっている米国では、白人よりも、黒人をはじめとするマイノリティ(社会的少数者)に深刻な影響をもたらしている。 たとえば、黒人の人口比率が30%のシカゴでは、新型コロナウイルス感染症による死亡者の60%を黒人が占めている。ニューヨークでは、黒人の人口比率が18%であるにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症の入院患者の3人に1人が黒人だ。
米ブルッキングス研究所では、2020年2月1日から6月6日までにアメリカ疾病予防管理センター(CDC)が発表したデータを元に、人種別の感染者数、死亡者数を分析。すべての年齢層において、黒人やラテン・ヒスパニック系のほうが、白人に比べて、新型コロナウイルス感染症による死亡率が高くなっていることを明らかにした。
これによると、55歳から64歳までの黒人の死亡率は65歳から74歳までの白人よりも高く、65歳から74歳までの黒人の死亡率は75歳から84歳までの白人よりも高い。なお、ラテン・ヒスパニック系の死亡率は、白人と黒人の中間だった。 年齢層別の死亡率の格差は、より若い年齢層で顕著で、45歳から54歳までの白人の人口比率は62%だが、この年齢層の死亡者のうち、白人の割合は22%にとどまった。黒人やラテン・ヒスパニック系の死亡率は白人の6倍以上にのぼる。
雇用や住宅、教育、健康など、様々な面で、黒人をはじめとするマイノリティへの社会経済的不平等が、新型コロナウイルスへの感染リスクや重症化リスクを高める要因となっている。
「医療格差によってマイノリティの人々が毎日、命を失っている。肌の色ゆえに、健康的に生活を送ることができず、早く亡くなってしまう」のが米国の現状である。マドンナが「コロナウイルスは平等をもたらす(金持ちも貧乏人もコロナに感染し、結果的には平等をもたらす)」と発言して激しく非難されたが、コロナウイルスは社会的弱者に最も激しく襲 い掛かるものなのだ。
さらに、「自由の国アメリカ」には、個人の自由を声高に主張して、平等を顧みない隠然たる勢力が存在する。他者の身体や正当に所有された物質的、私的財産を侵害しない限り、各人が望む全ての行動は基本的に自由であると主張し、個人的な自由に加え経済的自由も重視する「リバタリアン(Libertarian)」と称される自由至上主義者たちがそうで、近年、若い白人層に広がっているという。個人の自由が(経済的)平等や公共の福祉といった政治的目標に優先するとする立場で、金持ち、エリート層が多く、徹底した個人主義者であるため結束力が弱いので、政党として機能することはないが、全米で1割弱こうした考えの持ち主がいると言われ(5%未満という説もあるが)、無視できない存在となっている。
リバタリアンは経済活動(市場)への国家の介入を認めない、もしくは最小限に考えるため、連邦政府あるいは州が行ったコロナ対策の様々な制限には強く反対しているが、アンチマスクのような感情的な反発ではなく、いわゆる党派色のない立場で、例えば、中国からの渡航禁止の効果に対して、世界保健機関事務局長の「渡航制限は、情報共有、医療サプライチェーン、経済への悪影響によって害をもたらす」という発言と渡航制限が疫病の蔓延について遅延効果しかないことを引用し、その有効性に疑問を呈するなど冷静かつ客観的な批判を行っているのが特徴であり、検討に値するものも多く、一見進歩的でリベラルな考えを持っているように見える。
しかし、リバタリアンたちは自らが自立した個人で、自己決定が可能とみなし、他者に依存することなく生きていける強い人間という認識を持ち、強いエリート意識がある。米国のリバタリアンは銃によって自分の身は自分で守り、自分の労働で生活するという建国時点の理念を取り戻すことを意図しているが、これは一種の建国神話であり、建国時から米国は先住民の収奪、黒人奴隷の労働によって成り立ち、それが今日まで続いてきた事実を無視している。リバタリアンは人々の自由が最大限保証されるべきと唱えているが、人々が自由を行使する適切な能力や機会を有しているかについては配慮していない。形式的自由の平等な保障のみ擁護し、人々が実質的に自由か否かについては関心をもっていない。つまり、米国のリバタリアンは、極端なまでに個人的自由を主張しながら、現実の社会間の不平等には目をつぶる米国社会を象徴する存在なのだ。彼らにとって国家が行う福祉施策とは、「所有権の秩序に介入し能力・財産に恵まれた者を搾取して、能力・財産に恵まれない者の福祉を向上させることは端的に不公平であるのみならず、能力・財産に恵まれた者の活動意欲を阻害して結果的に政府・国家の、ひいてはそのサービスを受ける能力・財産に恵まれない者の福祉をも低下させかねない」ものなのだ。人間を「能力・財産に恵まれた者」と「能力・財産に恵まれない者」に分けることも大いに問題だ。このような単純な決めつけは時代錯誤と言ってよい。かなり前にヒットしたポップソングのタイトル”You Can Make It If You Try”はオバマ前大統領が好んで引用していたが、努力しても報われない人々が数多くいる現実を直視しない楽観的かつ「能力主義(メリトクラシー)」の米国を象徴する言葉だ。
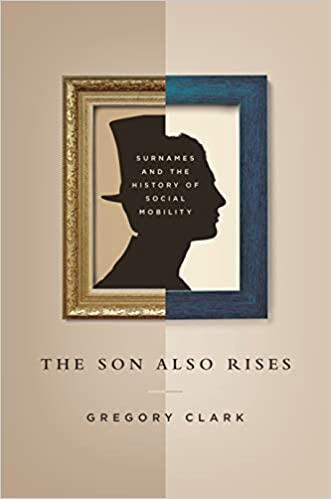
The Son Also Rises
アメリカン・ドリームというものがある。米国における成功の概念で、均等に与えられる機会を活かし、勤勉と努力によって勝ち取ることの出来るものとされ、その根源は独立宣言書に記された幸福追求の権利に拠っている。しかし、現実はどうだろうか。 経済学者グレゴリー・クラークは『The Son Also Rises』(ヘミングウェイにちなんだ著書では他にA Farewell to Almsがある)という著書で、英国における所謂特権階級、富裕層の姓を基にその社会的地位(×収入)の変化を800年間にわたって(記録がある限り)調べ、さらにその方法を米国などにも広げて出した結論は、個人の自由と権利を保障し、義務教育など社会的流動性を高める試みが長年行われてきた民主主義国家においても、社会的流動性(下層から上層への動き)は驚くほど低く、つまり、金持ちは金持ち、貧乏人は貧乏人の図式が基本的に大きく変わっておらず、固定化してしまっていると指摘している。つまり、既得権を持つ層は常に有利で、既得権のない人々は常に不利な状態にあるのが、封建社会でもない、近代以前の社会でもない、現代社会なのだ。これは建国から250年に満たない米国においても著しく、白人で既得権を持つ層に基盤を持つリバタリアンたちの論は自分たちの権利すなわち既得権を守り、持たない者を排除するものだと言っても良い。少なくとも米国以外の国ではそのように非難されるに違いない。と書いた後で、『White Trash』(ナンシー・アイゼンバーグ 2016)という400年間にわたる米国における階級の歴史を描いた本を読み、英国その他の地域からアメリカ大陸に意図的に送り込まれた白人貧民層の存在を知った。つまり、米国は土地を収奪され搾取されたネイティヴアメリカン、奴隷として使役されたアフリカ原住民、最下層の奉公人あるいは労働者として、あるいは厄介払いの対象として送り込まれた貧困白人の「犠牲」の上に成り立っており、未だそのツケが支払われていない国なのだ。これを無視しては現在の米国の問題は語れないだろう。
米国では従来から、「大きな政府の繰り出す政策で住民の安全を図る」との「大きな政府論」に対し、「政府の機能は最低限で良く、安全は自分たちで守る」との米国保守独特の「小さな政府論」(リバタリアンが求める政府は、暴力、盗み、詐欺からの保護、契約の履行の強制に限定される「最小国家(Minimal State)」)が対立しており、欧州を中心とする他の民主主義国家と比べれば、これまでは「小さな政府論」が優勢だった。しかし、コロナ危機を経験することで、「大きな政府論」が、「小さな政府論」をこれまで主張してきた共和党を巻き込む形で優勢となり始めている。世界最大規模のコロナ感染によって黒人差別の問題がさらに顕在化し、米国民は自分の国が格差社会であることをあらためて思い知らされることになり、格差是正のため、危機に対する対応力の強化のためには「大きな政府」が必要だとの考えがより浸透し、コロナウイルスがもたらす変化の兆しが見え始め、次期大統領選挙で民主党候補者が有利と予想される一因となっている。 むろん、リバタリアンの主張する「最小国家」では個人の努力の範疇を超えた未曽有の危機に対応できないのだ。
(5)へつづく

